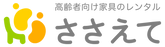高齢の方がいる家庭での簡単にできる滑り止め対策
高齢の方が自宅で暮らしていると、つい家具を支えに移動したり、とっさの時につかまったりすることは珍しくありません。しかし、その家具が本当に十分な支えになるのかについては、よく確認しなければなりません。
家具が滑ると、支えにした時にバランスを崩して転倒したり、車イス等で移動している時にぶつかったりといった問題も出てきます。そこで今回は、家庭で簡単にできる家具の滑り止め対策についてご紹介します。
家具を安定させて置くことの重要性
家具は、私たちの暮らしにとって欠かせないものです。さらに、心地よい住まいづくりを考える上では、家具の利便性やデザイン性だけでなく、安心して使えるかどうかにも気を配る必要があります。
特に、高齢の方にとって、安全性は重要です。グラつく状態で設置したり、簡単に倒れたり滑ったりするようでは、使い勝手が悪く怪我のもとにもなりかねません。高齢者がいる家庭では、小さな家具にも目を向けて、安全対策を考えていくことが求められます。
【家具別】効果的な滑り止め対策

それでは、効果的な滑り止め対策について家具ごとに見ていきましょう。今回は、家庭で簡単に、あまり費用をかけずに出来る方法をご紹介しています。
椅子
椅子の滑り止めは、ゴム製の脚カバー(ゴムキャップ)や滑り止めパッドが便利です。脚カバーの中には、椅子を滑りやすくする目的で製造されているものもあるため、目的に合ったものを選ぶよう注意しましょう。これらの製品は、滑り止めだけでなく、床材の保護にもつながり一石二鳥です。
テーブルの脚
テーブルの脚は、滑り止めシートやパッド、マットを上手に活用して安定感を高めましょう。大きくてしっかりしたダイニングテーブルの場合は、そう簡単に滑ることはないでしょうが、1人用の小さなテーブルなどは軽くて簡単に倒れたり、滑ったりする可能性があります。
テーブルの天板
食事時の食べこぼしによる掃除を簡単にするために、テーブルクロスを使用している家庭も多いです。しかし、少し引っ張っただけで滑り落ちてしまうものだと、床に落ちたクロスに足をとられて転倒したり、とっさに支えにしようとした時に手が滑ってバランスを崩したりする危険性があります。
テーブルクロスを使用したい場合は、滑り止めシールや滑り止めマットを活用して、クロスがズレてしまわないよう対策してみてはいかがでしょうか。
ベッド
介護用のベッドは、重く安定性があるためそう簡単に動かすことができません。しかし、簡易ベッドなど軽いものに関しては、ベッドからの立ち座りの振動でズレてしまうこともあるでしょう。
ベッドそのものが動かないように、ベッドの脚には滑り止めマット等を敷きましょう。ベッド専用の滑り止めアイテムがあれば、それを使用するのが一番かもしれませんが、ない場合は滑り止めシート等で代用するのもおすすめです。
さらに、ベッドからの立ち座りを安定させるために、立ち座り時に足をおろす場所に滑り止めマットを設置しておきましょう。
ソファ

どっしりして見えるソファも、寄りかかって座ったり、ドシンと座ったりすると、意外と簡単に位置がズレてしまいます。簡単に滑って位置が変わるようなソファは、落ち着きにくく床も傷つきやすいため、ズレ対策は必須と言えるでしょう。
まずは、滑り止めマットを活用して、ソファの位置がズレないよう対策しましょう。滑り止めマットは、ゴム製のものやシリコン製、フェルト製など色々なものがあります。
その他の滑り止めグッズ
ここまでご紹介したもの以外にも、滑り止めに役立つグッズはたくさんあります。特に取り入れたいものをいくつかご紹介します。
滑り止めワックス
フローリングが滑ってしまう場合は、専用のワックスを使って対策することが可能です。ワックスは、剥がれてしまうと滑りやすくなるため、定期的にメンテナンスする必要があります。
重量増加用ウェイト
軽い家具で滑り止めマット等を使っても不安がある場合は、ウェイトを使って安定性を高める方法もあります。脚にウェイトを巻き付けて重みを加えると、より滑りにくくなるでしょう。
ノンスリップテープ
ノンスリップテープは、一般的に細かな溝が入ったテープで、階段に貼って滑り落ちないよう対策する時に役立ちます。また、キャスター付きの家具の停止位置に貼ることで、必要以上にキャスターが動かないようにすることもできます。
家具の滑り止めで高齢者の暮らしの安全性を高めよう

家具が簡単に滑ったりズレたりすると、思わぬ怪我につながる可能性があります。今回ご紹介した滑り止めの対策では、絶対に滑らない・ズレない状態にはならないかもしれませんが、何も対策をしない場合に比べると格段に安全性を高めることはできるでしょう。
家具に全体重を預けなければならないほど、高齢の方の足の力が弱っている場合は、その他の補助具や福祉用具等も上手に活用して、できるだけ安全に過ごせる環境づくりを考えていきましょう。